BLOGブログ
 障害について知る
障害について知る
2025.03.25 火
きこえない・きこえにくい人へ情報を届ける大切なアプローチ〜2050年、4人に1人が難聴と予測〜

世界保健機関(WHO)の調査結果によると、世界で聴覚障害のある人は約4億6,600万人と推定。これは世界人口の5%以上(20人に1人)にあたります。
また、2050年までに世界で約25億人(4人に1人)が難聴を抱えて生活するだろうと予測されているのです。
この予測通りなら、研修会やセミナーを開催する場合、参加者の4人に1人が「きこえにくい」と感じることになり、人ごとではありません。今回は、きこえない・きこえにくい人と円滑にコミュニケーションするためのちょっとしたコツをレポートします。
■聴覚障害者への配慮・理解度チェック
まずは、「聴覚障害者への配慮」について、自分の理解度をチェックしてみましょう。
次の5つの問題をYes or Noで答えてみてください。(答えは、本文中と記事の最後にあります)
| Q1 | 耳が不自由な人は、みんな手話言語を使って話す | Yes or No |
| Q2 | コミュニケーションの方法は、専門家に聞けば十分 | Yes or No |
| Q3 | 手話通訳者がいても、要約筆記や字幕機能は必要 | Yes or No |
| Q4 | 資料の漢字に読み仮名を振るのは効果的である | Yes or No |
| Q5 | 「視覚的に伝えること」が重要 | Yes or No |
■コミュニケーションの方法は人それぞれ
「耳が不自由な人は、みんな手話言語を使って話す」と思い込んでいませんか?これは誤解です。全くきこえない「ろう」の人や、補聴器や人工内耳などで多少きこえる「難聴」の人がいるので、コミュニケーションの方法もさまざまなのです。
※コミュニケーションの一例:
 |
手話・ 手話通訳 |
中途失聴者や難聴者の多くは、聞くことに障害があるだけで、話すときには日本語。手話での会話が難しいときは、身振り手振りで伝える |
 |
口話 | 相手の視界に入って、普通の声の大きさで、はっきりとゆっくり、文節を区切って話す |
 |
筆談・ 要約筆記 |
筆談器やメモ用紙を使って筆談をする。話すことを全部書く必要はなく、キーワードや短い文章で書く |
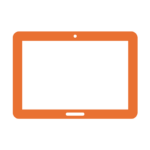 |
スマホ・ タブレット |
筆談器の代わりに使用したり、文字と音声を互いに変換できるアプリなどを利用 |
厚生労働省の調査によると、聴覚障害者のコミュニケーションは、手話・手話通訳が25%、口話が10%、筆談・要約筆記が23%、スマホ・タブレットが21%となっています。 どのような方法が1番良いのでしょうか?
コミュニケーションの方法は、専門家の意見だけでなく、当事者から教えてもらうことが大切です。 また、対面での会話はきこえても、ビデオの音声やマイクを通した音声をきき取りづらい人もいるので、研修会などでは配慮が必要となります。
| 便利なアプリが続々登場! ●聴覚障がい者等支援アプリ「こえとら」 https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/cases/case_0019.html ● 声や音を見える化する独自のアルゴリズム「ワイワイシステム」 https://yysystem.com/ |
■事前準備で9割決まる?!
研修会やセミナーを開催する時は、どのようなことに配慮すれば良いのでしょうか?
※事前準備の例:
 |
集客するとき | 手話や要約筆記など必要なサポートがあるか? 参加者に事前に確認する |
 |
会場設営や運営面 | 手話通訳者を見やすい席、講師やスタッフへの教育 |
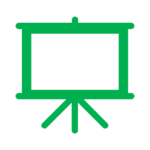 |
資料 | スクリーンに映す資料には字幕機能を付ける 漢字には読み仮名を振る 「やさしい日本語」を使用するなど |
よく「手話通訳者がいるのだから、要約筆記や字幕機能はいらないのでは?」と質問されることがあります。しかし、きこえない・きこえにくい人は、手話が得意な人・苦手な人、日本語が得意な人・苦手な人などさまざまです。
きこえる人にとっても、講師の話の他に、要約筆記や字幕機能があると、理解を助けるという効果もありますよね?

また、「資料の漢字に、なぜ読み仮名を付ける必要があるの?」と不思議に思っている方もいるのではないでしょうか?きこえない・きこえにくい人は、音声で読み方を習得していないので、どのように読むのか?悩んでしまう人も一定数いるのです。特に学校では習わない略称や略語には、読み仮名を付けることが大切です。
読み仮名は、きこえない・きこえにくい人以外にも、漢字が苦手な人、外国人などにとっても、分かりやすくなる配慮です。
| ブライトでは、当事者団体と連携しながら、聴覚障害者向けの「対応マニュアル」「事前準備チェックリスト」などを作成しています。 ご興味のある方は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。 |
■きこえない・きこえにくい人には「視覚的に伝えること」が重要
2025年11月、「東京2025デフリンピック」が開催されるのをご存知ですか?「デフリンピック」とは、4年に一度開催される「きこえない・きこえにくい方」のための国際的なスポーツ大会です。この大会の工夫が、とても参考になるのです。

※音の代わりに視覚で伝える一例:
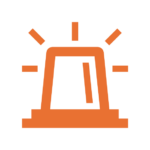 |
フラッシュランプ | 陸上や水泳では、スタートの合図の音の代わりに、光で知らせる装置を使う |
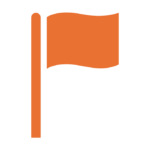 |
フラッグ | サッカーでは、ファウルをした時に、審判が笛を鳴らすのと同時に旗や手をあげて選手に知らせる |
これらは、研修会にも応用できそうです。
例えば、緊急時の警報や非常ベルなどがきき取りにくい人は、危険な状況が伝わりにくい場合があるので、光でのサインは効果的です。また、ワークショップなどを行う際、誰が発言しているのか分かりにくいことがあるので、旗や手を挙げて発言するとスムーズです。
■最後に・・・
以上の内容は、ほとんどが当事者本人から教わった事です。相手の人格を尊重し、理解しようという気持ちは、障害の有無に関係なく大事なことですよね。
ところで、海外旅行で現地の人から「こんにちは」「ありがとう」と日本語で話かけられると嬉しい気持ちになりませんか?
そこで、研修会で使える手話言語を1つ覚えてみましょう!
右こぶしを鼻から前に開き、頭を下げる
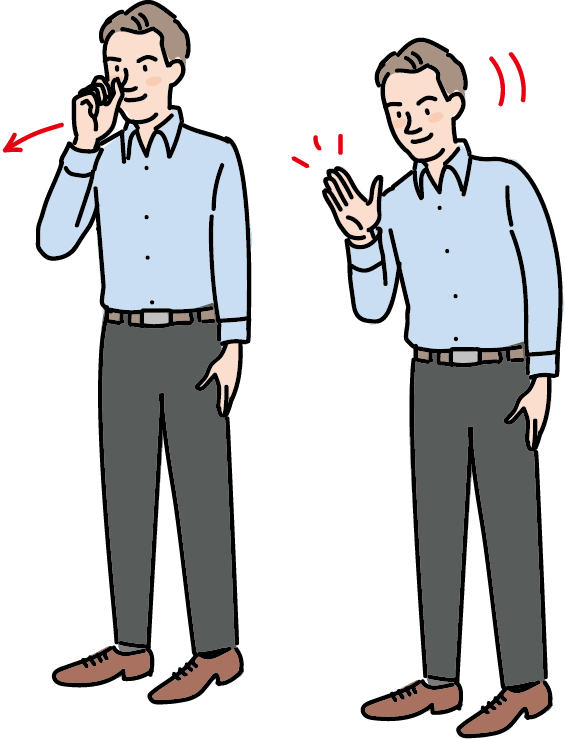
「よろしくお願いします」の手話言語は、いろんなシーンで使えそうですね!
■Q1〜Q5の答え:
Q1. 耳が不自由な人は、みんな手話言語を使って話す →No
Q2. コミュニケーションの方法は、専門家に聞けば十分 →No
Q3. 手話通訳者がいても、要約筆記や字幕機能は必要 →Yes
Q4. 資料の漢字に読み仮名を付けるのは効果的である →Yes
Q5. 「視覚的に伝えること」が重要 →Yes
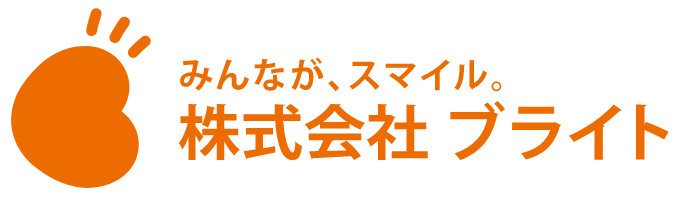
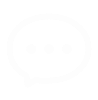 相談をする
相談をする