BLOGブログ
 ユニバーサルデザイン
ユニバーサルデザイン
2025.05.07 水
立命館守山高校の学生に講座を開きました ~「伝える」って、どういうこと? 情報のユニバーサルデザインを高校生と考える時間~

2025年4月22日、立命館守山高校のフィールドワーク課題の一環として、在校生のNさんからインタビューを受けました。
当日は、私・南條と小川の2名で、ブライトとしてお話をさせていただきました。
きっかけは「左利き」である、ということ
Nさんは自身が左利きであることをきっかけに「左利きの人が生きやすい社会」というテーマに取り組まれており、そこからユニバーサルデザイン(以下:UD)に興味を持たれたそうです。
実はブライトでは、2022年にも「左利きであること」をテーマにUDに興味を持った高校生からインタビューを受けていました。
こうした“個人の体験”が出発点となって社会課題に目を向けていくプロセスは、とても素晴らしいことだと感じます。

情報のUDとは? どのように進めていくのか
インタビューは「UDをどのように企画・設計していくのか」というNさんの質問からスタート。ブライトからは2つの事例を元にプロセスをお話しました。
<多くの方に伝わるツールづくり>
まず、情報ツール制作の例として空港スタッフへのマナー研修ガイドブック制作の事案を紹介しました。
全空港スタッフ向けにガイドブックを制作した翌年、日本語が得意ではない外国人スタッフへの教育が課題となっていました。
そこでブライトでは難しい言葉や表現を平易にして、わかりやすくした「やさしい日本語」を提案。これを採用いただき在留外国人スタッフをフォローすることが可能に。
更に今年は13ヶ国語に対応したアニメーション動画へ展開。より受け手が自分にとって受け取りやすいツールを選べるようになったという事例です。
【交通】”やさしい日本語”を用いたマナーガイドで外国人空港スタッフのマナー改善

<UDのコンサルとは?>
ツールを用意するだけではなく、「情報を届けたい人」と「受け取りたい人」をつなぐのがブライトの仕事です。
たとえば聴覚障害のあるアスリート向け研修では、日本ろうあ連盟に協力をいただきながら、当事者の意見をもとに設計。本人たちの視点に寄り添う形で内容を組み立てた事例をお話しました。
共通して大切にしているのは、“丁寧なヒアリングにより課題を明確にすること”と“当事者の声を集め、反映させること”。情報を発信する側の視点だけで作ってしまうと、つい専門的な言葉や情報量が多くなってしまい、「読むのが大変」「意味が伝わりにくい」といったことが起こりがちです。
だからこそ“誰に届けたいのか”“その人はどんな言葉で理解するのか”を明確にし、当事者と一緒に考えることで、ようやく「届く情報」になる、と、(もう少し砕けたテイストで)お話ししました。
UDの“7原則”は大切。でも、それだけでは「判断の軸」にはなりにくい
Nさんからは「UDを作る時、7原則満たしているという判断はどのように行っているのか(どのような基準を用いているか)。」「7原則だけではフワッとしており曖昧なのでは」という質問が。鋭い。
UDの7原則は、すべての人ができるだけ平等に使える製品・環境・サービスを設計するためのガイドライン。以下のように定められています。
| 1. 公平性 2. 自由度(柔軟性) 3. 単純性 4. 分かりやすさ 5. 安全性 6. 省体力 7. 空間性 |
(詳しくはこちら:https://bright3.jp/universal-design/)
ただし、確かにNさんの言うように、この7原則だけでは“判断の軸”としてはやや抽象的で、ビジネス上の実装には課題があります(もちろん、ベースの考え方としては重要でUDの礎を構築したとても大切な原則です)。
そこで、ブライトでは情報のUDに関して次のような基準を用いている、ということをお伝えしました。
・Webサイト:JIS X 8341-3:2016(高齢者・障害者等配慮設計指針)に基づくアクセシビリティ対応
すべての人がウェブサイトを利用しやすくするための国内規格で、特に高齢者や障害のある方に配慮した設計を求めるものです。
例えば、「音声読み上げに対応しているか」「キーボードだけで操作できるか」など、誰にとっても情報にアクセスしやすいよう設計することが求められます。
※アクセシビリティに配慮した事例:金融ADRによる情報保障のお手本として評価されたホームページ
・印刷物などのツール:Webアクセシビリティほど普及している明確な基準はありませんが、ブライトでは国際規格「ISO/IECガイド71」をもとに、文字サイズや色のコントラストなど独自の基準を構築し、誰にでも伝わる設計を目指しています。
大切なのは「現実に落とし込むための仕組みや判断基準」を持つことです。

「万人向け」って、誰かを排除することにならないの?
議論はさらに深まり、Nさんからこんな問いも出てきました。
「UDで“万人向け”を目指すことが、逆に特定の人にとって使いづらいものになることはありませんか?」
視覚障害者向けに設置した点字ブロックが、車椅子利用者には障害になってしまう――そんな事例がハード面ではあります。
ですが、情報のデザインにおいては、「複数の伝え方=選択肢を用意すること」ができます。
つまり、伝えたい人に合わせて、伝え方を工夫することができる。たくさんの道を用意することができます。
例えば…
・高齢者には、読みやすく簡略化したリーフレット
・若年層には、SNS動画やWebコンテンツ
・視覚障害者には、点字や音声コード。聴覚障害者には、手話や字幕。
・在留外国人には、やさしい日本語 などなど
このように「同じ情報でも、相手に合わせて届け方を用意する」ことが、私たちの仕事です。
(もちろん、予算や時間などの制約の中で情報をつくる現実もあります。
すべてのニーズに対応できるわけではないからこそ、「誰に一番届けたいか」を明確にしたうえで、優先順位を立てることも重要ですね。)
紙媒体とデジタル、それぞれのUDの違いは?
終盤に「紙とデジタル、それぞれで気をつけるUDの違いはありますか?」という質問がありました。
ブライトとしては「根底は同じ」だと考えています。
もちろん、媒体ごとの技術的な違いはありますが、大事なのは“課題と目的を見極めたうえでプランニングをすること”、そして“当事者の声を丁寧に聞くこと”。
どんなアウトプットでも、この姿勢があれば情報は届くようになる、という話をして1時間半に及ぶインタビューはお開きになりました。


Nさんがブライトを選んでくれたのは、
「UDといえば“物”という印象が強かったが、ブライトでは“情報”を伝えるUDという考え方があり、これからの情報社会ではこうした視点も必要なのではないかと感じた」からとのこと。
「情報のUD」という視点に興味を持ち、わざわざ滋賀から来てくださったことに、私たちも驚きと喜びを感じました。今回のインタビューを通して、あらためてブライトの大切にしていることや日々の業務を見つめ直す、貴重な機会となりました。
Nさんの今後の取り組み、心から応援しています!
参考URL
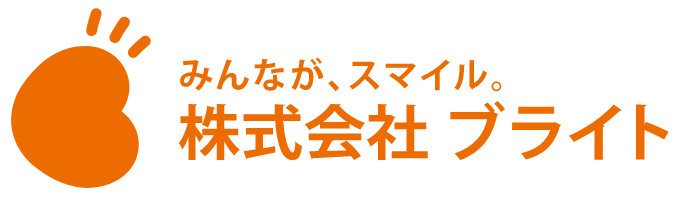
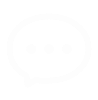 相談をする
相談をする